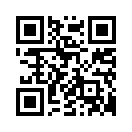2007年07月17日
祇園祭2007・長刀鉾曳き初め 7月12日
7月10日に始まった鉾建てが、12日には曳き初めとなりました。
この日だけは、女性も子供も鉾を曳くことができるのです。(鉾町によって、異なるようですが)
特に、長刀鉾はお稚児さんが乗り込んで、"太平の舞"を披露してくれるのです。
7月5日の稚児舞披露の時とも、また17日の巡幸当日とも、
それぞれに、お稚児さんの衣装が違うのです。
お稚児さんは、みんなの前に姿を現すたびに衣装が変わってゆきます。
まるで幼虫から蝶へ成長する間に、何度か脱皮を繰り返すように、
可愛い姿から、華麗な姿へ。そして、豪華絢爛なお稚児さんへと、冠・衣装が変化していくのです。

囃方の子供たちが、曳き初めでやってきた友達と声を交わしています。

お稚児さんたちも、知ったか顔を下にみつけたのでしょうか。
瞬間、普段の子供の顔がのぞきましたね。

「よぉーい、よぉ~い!えぇ~ん、や~ら~やぁ~!」
さあ、音頭取りの掛け声にあわせて、綱を曳きましょう。
最初の曳き始めは、なかなか動かないですよ。
物理で言うところの、慣性の法則を感じる瞬間です。



稚児舞が始まりました。
実際に鉾の上で”太平の舞”を舞うのは、これが初めてじゃないでしょうか。

蝶とんぼの冠が、緊張した表情の中にも、お稚児さんの可愛さを際立たせています。
思いっきり前に乗り出して、上半身は完全に鉾から出ています。
後ろからしっかりと帯を摑んで、お稚児さんの体を支えているのが見えますね。






長刀鉾は、四条東洞院の町会所から柳馬場通まで東へ進み、
そこで、バックで町会所まで再び戻ってくるのです。
巡幸当日は、決して後退はしないですが、曳き初めは関係ありません。
曳き終わった後、鉾の入場券をみんな貰っていました。 地図はこちら
地図はこちら

この日だけは、女性も子供も鉾を曳くことができるのです。(鉾町によって、異なるようですが)
特に、長刀鉾はお稚児さんが乗り込んで、"太平の舞"を披露してくれるのです。
7月5日の稚児舞披露の時とも、また17日の巡幸当日とも、
それぞれに、お稚児さんの衣装が違うのです。
お稚児さんは、みんなの前に姿を現すたびに衣装が変わってゆきます。
まるで幼虫から蝶へ成長する間に、何度か脱皮を繰り返すように、
可愛い姿から、華麗な姿へ。そして、豪華絢爛なお稚児さんへと、冠・衣装が変化していくのです。

囃方の子供たちが、曳き初めでやってきた友達と声を交わしています。

お稚児さんたちも、知ったか顔を下にみつけたのでしょうか。
瞬間、普段の子供の顔がのぞきましたね。

「よぉーい、よぉ~い!えぇ~ん、や~ら~やぁ~!」
さあ、音頭取りの掛け声にあわせて、綱を曳きましょう。
最初の曳き始めは、なかなか動かないですよ。
物理で言うところの、慣性の法則を感じる瞬間です。



稚児舞が始まりました。
実際に鉾の上で”太平の舞”を舞うのは、これが初めてじゃないでしょうか。

蝶とんぼの冠が、緊張した表情の中にも、お稚児さんの可愛さを際立たせています。
思いっきり前に乗り出して、上半身は完全に鉾から出ています。
後ろからしっかりと帯を摑んで、お稚児さんの体を支えているのが見えますね。






長刀鉾は、四条東洞院の町会所から柳馬場通まで東へ進み、
そこで、バックで町会所まで再び戻ってくるのです。
巡幸当日は、決して後退はしないですが、曳き初めは関係ありません。
曳き終わった後、鉾の入場券をみんな貰っていました。

2007年07月17日
祇園祭2007・古式一里塚松錺り式 7月14日
今年も、松原中之町の「古式一里塚松錺り式」を覗かせていただきました。
台風4号が直撃コースを進みながら接近してきているので、
お天気は雨が降っています。
今年のお稚児さんのお家なら近かったので、
きっと、お練り(歩き)で来られると、楽しみにしていたのですが、
小雨、時には大雨、このお天気では諦めるしかないですね。 まったく持って残念です。
しかし、そんな失望感を吹き飛ばす、サプライズが待っていたのです。
そう、奥座敷で薄茶の接待を戴くことが出来たのです。
これは、行って誰でも戴ける訳ではありませんので、とっても幸運でした。

”木の実の菓子”と薄茶を水で点て、お稚児さんに振舞われるのが慣わしとなっていますが、
このお菓子は、"きぬた"で有名な『長久堂さん』で作られ、
松竹梅を模った意匠になっています。
ふくよかな松に、竹の葉と梅の実があしらわれています。
座敷の奥には、祇園社の祠があり、「一里塚松錺り」と神饌が見えています。

神饌がよく見えるように、拡大画像↓でどうぞ。
去年は見ることが出来なかった、左右のアラメ籠の車エビ三匹、鯛の尾頭付きも、
まだそのまま残っていました。
因みに、右が雄松、左が雌松。
根元の黒いのが、目籠にアラメを巻き覆ったもので、
それに車エビがそれぞれ三匹ずつ着けられています。
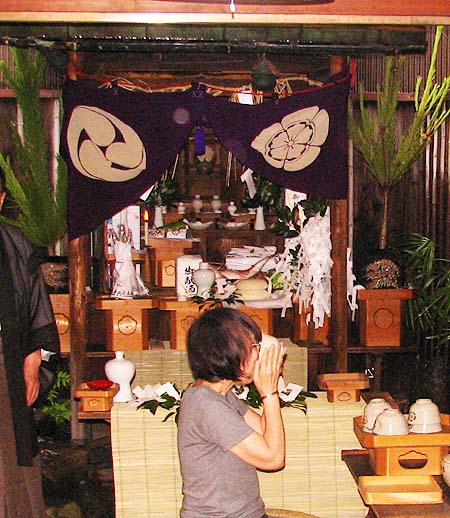
そうこうしていたら、あっという間にエビと鯛は下げられてしまいました。
この季節ですから、痛まないようにすぐに下げられるのです。

りっぱな真鯛でした。重さも相当ありそうで、腹の厚みがすごかったです。
お造りにして、お町内の方々に振舞われるそうです。
これは旨いでしょう。
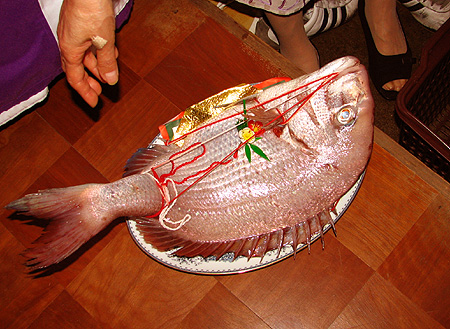
接待で戴ける薄茶というのは、抹茶に冷水を注ぎ茶筌で溶いたもので、
蒸し暑い京都の夏には、最適な飲み物ですね。
決して苦くなく、ほんのりとした甘みと爽やかな抹茶の香りで、
清々しい涼を愉しむことができます。



恥ずかしながら、私も戴いております。
茶道など無縁の私ですので、一瞬焦りましたが、
口の中で広がった抹茶の香りが、高ぶった気持ちを静かになだめてくれました。



短い時間でしたが、とても贅沢な体験をさせていただきました。ありがとうございました。
松原中之町の皆様には、この場で御礼申し上げます。

★この行事の詳細情報は、こちらもご参考に。 地図はこちら
地図はこちら
祇園祭2006 古式一里塚松飾 7月14日
祇園祭2006 中之町・神剣長刀の拓本
台風4号が直撃コースを進みながら接近してきているので、
お天気は雨が降っています。
今年のお稚児さんのお家なら近かったので、
きっと、お練り(歩き)で来られると、楽しみにしていたのですが、
小雨、時には大雨、このお天気では諦めるしかないですね。 まったく持って残念です。
しかし、そんな失望感を吹き飛ばす、サプライズが待っていたのです。
そう、奥座敷で薄茶の接待を戴くことが出来たのです。
これは、行って誰でも戴ける訳ではありませんので、とっても幸運でした。

”木の実の菓子”と薄茶を水で点て、お稚児さんに振舞われるのが慣わしとなっていますが、
このお菓子は、"きぬた"で有名な『長久堂さん』で作られ、
松竹梅を模った意匠になっています。
ふくよかな松に、竹の葉と梅の実があしらわれています。
座敷の奥には、祇園社の祠があり、「一里塚松錺り」と神饌が見えています。

神饌がよく見えるように、拡大画像↓でどうぞ。
去年は見ることが出来なかった、左右のアラメ籠の車エビ三匹、鯛の尾頭付きも、
まだそのまま残っていました。
因みに、右が雄松、左が雌松。
根元の黒いのが、目籠にアラメを巻き覆ったもので、
それに車エビがそれぞれ三匹ずつ着けられています。
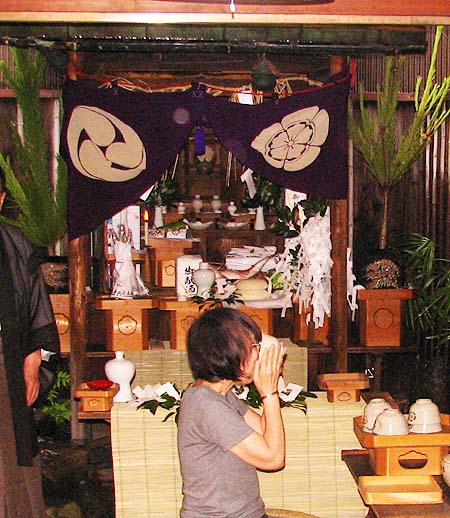
そうこうしていたら、あっという間にエビと鯛は下げられてしまいました。
この季節ですから、痛まないようにすぐに下げられるのです。

りっぱな真鯛でした。重さも相当ありそうで、腹の厚みがすごかったです。
お造りにして、お町内の方々に振舞われるそうです。
これは旨いでしょう。
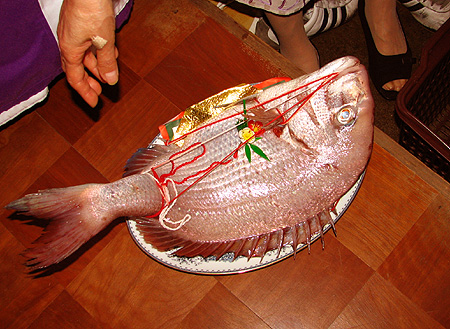
接待で戴ける薄茶というのは、抹茶に冷水を注ぎ茶筌で溶いたもので、
蒸し暑い京都の夏には、最適な飲み物ですね。
決して苦くなく、ほんのりとした甘みと爽やかな抹茶の香りで、
清々しい涼を愉しむことができます。



恥ずかしながら、私も戴いております。
茶道など無縁の私ですので、一瞬焦りましたが、
口の中で広がった抹茶の香りが、高ぶった気持ちを静かになだめてくれました。



短い時間でしたが、とても贅沢な体験をさせていただきました。ありがとうございました。
松原中之町の皆様には、この場で御礼申し上げます。

★この行事の詳細情報は、こちらもご参考に。
祇園祭2006 古式一里塚松飾 7月14日
祇園祭2006 中之町・神剣長刀の拓本